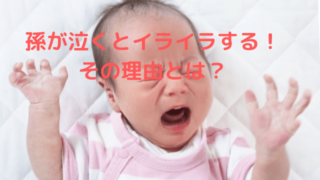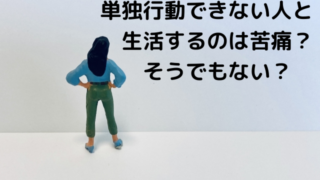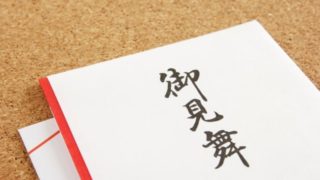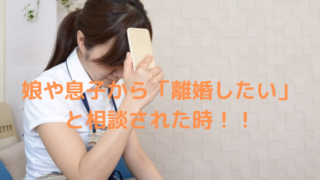いずれは親と同居するつもりでも、新婚早々から実家で同居する夫婦はとても少なくなっています。
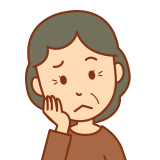
新婚生活は2人きりの方が楽しいでしょ

そこまで野暮じゃないよな
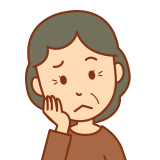
いずれ・・でいいのよね
義父母たちも、結婚してすぐに同居しようとは考えなくなっています。
昔は家を継ぐ長男夫婦は、結婚した時から親と同居するのが当たり前だったようですが、今の時代では少数派です。
昭和の時代の住宅事情を考えれば、二世帯、三世帯で暮らすのは難しいので核家族化が進んできたわけです。
ですが、いずれは同居するとしてもそのタイミング次第で上手くいく可能性に差が出てきます。
同居を予定しているのなら、成功させたいですよね。
失敗を防ぐためにも、同居を始めるタイミングは重要です。
同居のタイミングの重要性を考えてみましょう。
同居のタイミングによる問題点
結婚した相手の実家で、義理の親と同居する夫婦は、どのタイミングで同居をスタートしているのでしょうか。
同居を始めるタイミングによるメリットとデメリットを見てみましょう。
結婚と同時にスタート
結婚後にいきなり同居をスタートするケースは、今ではかなり珍しいと思います。
新婚夫婦と一緒に暮らすのは、親世代にとっても気を使うので、しばらく別居した方がお互いのためだと考える人たちが増えているからでしょう。
それでも結婚と同時に同居を始める夫婦がいないわけではありません。
メリットとしては、経済的なことが大きいと思います。
若い夫婦の場合、収入もまだ少ないですし、非正規で働いている人たちは安定もありません。
経済的に安定していない夫婦にとって、安心して暮らせる家があるのは助かります。
結婚してからは、子供が生まれればお金はさらに必要になります。
親たちに援助してもらうつもりで同居する夫婦もいるでしょう。
デメリットとしてあげるのであれば、嫁の立場になる女性のストレスです。
いきなり他人に囲まれて暮らすのは、想像以上に精神的な負担も大きいと思います。
結婚後数年経ってスタート
結婚して数年経ってから同居を始めるケースは、いずれは同居するつもりだったケースが多いですね。
子供が生まれてから同居するパターンや、実家をリフォームして同居しやすい環境に整えてからスタートするパターンです。
メリットは、すでに結婚して自分たちの家族の生活スタイルが確立されているので、そのスタイルを崩さないように線引きしやすいという点でしょう。
何か急いで同居しなければいけない事情が無い限り、時間をかけて計画し、同居しやすい準備ができます。
デメリットとしてあげるのであれば、きちんとお互いの生活区域を分けられない状況になると、価値観の違いなどでトラブルが起こりやすいと思います。
親の世話が必要になりスタート
親が元気でいてくれるのなら、同居するつもりはなかったとしても、介護が必要になれば考えなければいけません。
近くに住んでいるのなら、通いながらお世話することもできますが、遠方に暮らしているのであれば、通うのは難しいでしょう。
親の老後の生活を支えるために同居を始めるケースは、高齢化社会なので珍しくありません。
メリットとしてあげられることはほとんどなく、精神的、肉体的、経済的な負担も大きくなります。
ですが、遠方にいる親の心配をしながら暮らすよりも、一緒に居た方が安心できるので、その点はメリットと言えるのではないでしょうか。
誰もが健康なまま寿命を全うできるわけではないので、いつか来る日のためにきちんと準備していないと、デメリットしか感じない苦しい同居になると思います。
失敗しやすいパターン
夫の親と同居するタイミングとして、一番失敗しやすいのいつだと思いますか?
結婚と同時に同居をスタートするケースが、失敗しやすいと考える人が多いのではないでしょうか。
たしかに、新婚生活を楽しむ間もなく同居するのは、色々問題が起こりそうですよね。
結局は、別々に暮らすことになるケースも少なくありません。
ですが、一番失敗しやすいのは、結婚後しばらく経ってからの同居なのです。
その理由は、一つの家庭に主婦が二人存在することになるからです。
まだ家事をこなすのも未熟な新婚時期に同居をスタートした場合は、ベテラン主婦と見習い主婦という立場がハッキリします。
家事のやり方もまだ定まっていないので、姑に習いながら主婦のテクニックを身につけることができます。
しかし、結婚して数年以上も自分たちだけで生活してきた場合、すでに主婦としてのテクニックもありますし、自分のやり方が確立しています。
姑の家事のやり方が気に入らないと思う嫁と、嫁の家事に文句を言いたい姑・・。
失敗しやすいのは、すでに2つの家庭が出来上がっているのに、無理に1つにまとめようとするからです。
同居の成功パターン
同居が成功しやすいパターンをまとめてみると、3つのポイントが見えてきます。
住居を分離できる二世帯住宅
やはり同居が成功しやすいのは、キッチンやお風呂など水回りだけじゃなく、玄関から完全に分けている二世帯住宅です。
必要な時だけ顔を合わせられるし、助けが必要な時はすぐに駆け付けられる安心感があります。
お互いの生活を干渉しないように、きちんとルールを作って同居をスタートできれば、失敗する要素は少ないでしょう。
仕事を持っている
完全に住居を分けることができなくても、主婦が2人存在しないのなら、あまりトラブルになりません。
姑が仕事をしているのなら、家事は一切卒業してもらってもいいですよね。
逆に嫁が仕事をバリバリして、姑には家事をお願いするというパターンでもイイです。
お金を稼ぐためのサポートをする主婦への感謝の気持ちをしっかり伝えて、家族がそれぞれの役割を担えばいいのです。
細かいもめごとはあるでしょうが、それぞれにしっかり役割があるので、あまり大きな問題にならないはずです。
みんなで育児する
働きながら家事も育児も一人でするのはとても大変です。
夫の実家で親と同居できれば、育児のサポートが受けられるので、安心して働けます。
同居を考えていなかった人たちが、現実に育児と仕事の両立が難しくて、親と同居し始めるケースも増えているのです。
家族がみんなで子供を育てるという、昔ながらのスタイルが見直されているのではないでしょうか。
まとめ
結婚する前に、将来は夫の親と同居することについて考えるのであれば、どのタイミングで同居をスタートするのかも話し合っておくべきです。
いきなり同居するのは、たしかにちょっと抵抗を感じる人が多いと思いますが、何年も自分たちだけで生活してから同居する方が大変です。
できるだけ早い段階で同居を始められると、働きながら育児するのも協力を得やすいのではないでしょうか。
同居を成功させる最大のポイントは、親世代の協力をメリットとして受け入れられるかどうかです。
姑を疎ましく感じるから、全て一人でやってやる!と意地になって頑張る人もいますが、自分だけじゃなく家族みんなにしわ寄せが行ってしまうかも知れません。
同居の悪い点ばかり考えるよりも、良い点に目を向けて考えられるといいですね。